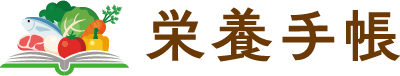寒さが厳しくなってくると、手足や体全体が冷える「冷え性」に悩む方が増えてきます。
冷え性は、単に体温の低下が原因ではなく、体の中で起こっている様々な不調のサインであることが多いです。血行不良や栄養不足、筋肉量の不足など、体の内側から整えることが冷え性改善のカギとなります。
今回は、冷え性改善に効果的な栄養素について、鉄分やビタミン、タンパク質を中心にご紹介します。
冷え性の原因とは?
冷え性は一般的に言うと女性に多く見られる症状ですが、実は男女問わず多くの人が悩んでいます。冷え性の主な原因は以下のようなものがあります。
- 血行不良:血液の流れが悪くなると、手足など末端部分に十分な血液が届かなくなり、冷えを感じやすくなります。
- 自律神経の乱れ:ストレスや不規則な生活習慣により自律神経が乱れると、体温調節がうまくいかず、冷えを感じることがあります。
- 栄養不足:体の熱を産生するためには、十分な栄養が必要です。特にエネルギーを効率よく産生するための鉄やビタミンが不足すると、体が冷えやすくなります。
- 筋肉量の不足:筋肉は体内で熱を産生する重要な器官です。筋肉量が少ないと基礎代謝が低下し、体内での熱産生が十分に行われなくなります。
これらの要因が複合的に作用して冷え性が起こるため、外からの温め対策だけでなく、体の中からも冷えを改善するためのアプローチが必要です。
鉄の重要性 -血液の巡りを良くする‐

冷え性の原因として特に注目されるのが、貧血による血行不良です。鉄は血液中のヘモグロビンを構成する重要な成分で、酸素を全身に運ぶために重要な役割を担っています。鉄が不足すると、十分な酸素が体の隅々まで行き渡らず、手足の先など末端部分が冷えてしまうことがあります。
鉄が不足する原因には、食生活の乱れによる摂取不足や月経や出産による鉄の喪失、胃腸の不調による吸収不良などがあります。特に女性は月経や出産によって鉄を失いやすく、貧血になりやすい傾向があるため、意識的に鉄を摂取することが大切です。
鉄を豊富に含む食品には、レバーや赤身の肉、あさりなどがあります。
ビタミンB群とエネルギー代謝 ‐熱産生を助ける‐
ビタミンB群は、体内でのエネルギー代謝を助け、冷え性改善に役立つ重要な栄養素です。ビタミンB群には、糖質、脂質、タンパク質などの栄養素をエネルギーに変換するために重要な役割があり、これによって体内で熱が産生されます。
ビタミンB群の中でも、特に冷え性改善に関連するものには次のものがあります。
- ビタミンB1:糖質をエネルギーに変えるために重要な働きを持ちます。不足すると、エネルギー産生ができず体が冷えやすくなります。ビタミンB1は豚肉や豆類に多く含まれており、良質なたんぱく源としてもおすすめです。
- ビタミンB6:タンパク質の代謝を促進し、エネルギーを効率よく産生する役割を果たします。ビタミンB6は、鶏肉や魚類などから摂取できます。
これらのビタミンB群を多く含む食材を日常的にしっかり摂取することが大切です。
タンパク質で体を温める -筋肉量の維持と増加‐

体内での熱産生には、筋肉が大きく関わっています。筋肉はエネルギーを消費して熱を産生するため、筋肉量が多いほど基礎代謝が高くなり、体内での熱産生も増えます。反対に、筋肉量が少ないと、基礎代謝が低下し、体の中で十分な熱が作られず、寒さを感じやすくなります。
特に女性や高齢者は筋肉量が少なくなりがちですが、適切な運動とともに、良質なタンパク質を摂取することで筋肉を維持・増加させることができます。
タンパク質を豊富に含む食品には、以下のようなものがあります。
- 鶏肉、豚肉、牛肉などの肉類
- 魚介類(鮭やマグロ、サバなど)
- 大豆製品(豆腐、納豆、豆乳など)
- 卵
これらの食品をバランス良く取り入れ、定期的な運動と組み合わせることで、筋肉量を維持し、冷えに強い体を作ることができます。
その他の冷え性改善に役立つ栄養素
冷え性改善には、鉄分、ビタミンB群、タンパク質以外にも下記の栄養素が役立ちます。
- マグネシウム:筋肉の弛緩を助け、血管を拡張するため血行を促進します。アーモンド、ナッツ類、ほうれん草などに多く含まれています。
- ビタミンE:血液循環を改善し、末端の血行を良くします。アーモンドやヒマワリの種、植物油に豊富に含まれています。
- オメガ3脂肪酸:血液の流れをスムーズにし、炎症を抑える働きがあるとされています。青魚(サバ、イワシなど)や亜麻仁油、チアシードに含まれています。
これらの栄養素も食事に取り入れることで、より効果的に冷え性を改善することができるでしょう。
まとめ
冬の寒さに対抗するためには、外からの防寒対策だけでなく、体の内側から冷えを改善するための栄養が欠かせません。鉄やビタミンB群、タンパク質を意識的に摂取することで、血行やエネルギー代謝を改善し、体を芯から温めることが可能です。
冷え性は長期間の生活習慣の積み重ねによるものが多いため、日々の食事や運動を通じて体質改善を目指しましょう。バランスよく栄養を取り入れ、寒い冬を快適に乗り越えるための準備を始めてみてください。
オーソモレキュラー栄養療法の基本
オーソモレキュラー栄養療法では、特定の不足栄養素を補う前に、基礎的な栄養素(主に、タンパク質、鉄、ビタミンB群)がヒトの体の土台作りの材料として重要と考えています。これらの栄養素の体内バランスを整えた上で、不足している栄養素を補うことで、健康維持や不調の改善を目指します。

水流 琴音(つる ことね)
「暮らしのなかで自然にふれる」やさしい食を台所から育む
【所持資格】
管理栄養士、一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所 認定ONP(7期)
【活動・経歴】
フリーランス管理栄養士として活動中。
オーソモレキュラー栄養療法を取り入れたクリニックで栄養カウンセラーとして勤務。
また、クリニックでの栄養療法の導入支援やスタッフ研修も行っている。
その他、フリーランスとして予防医療に関する発信や執筆、一般向けセミナー講師としても活動中。
【SNS】
Instagram